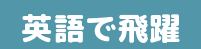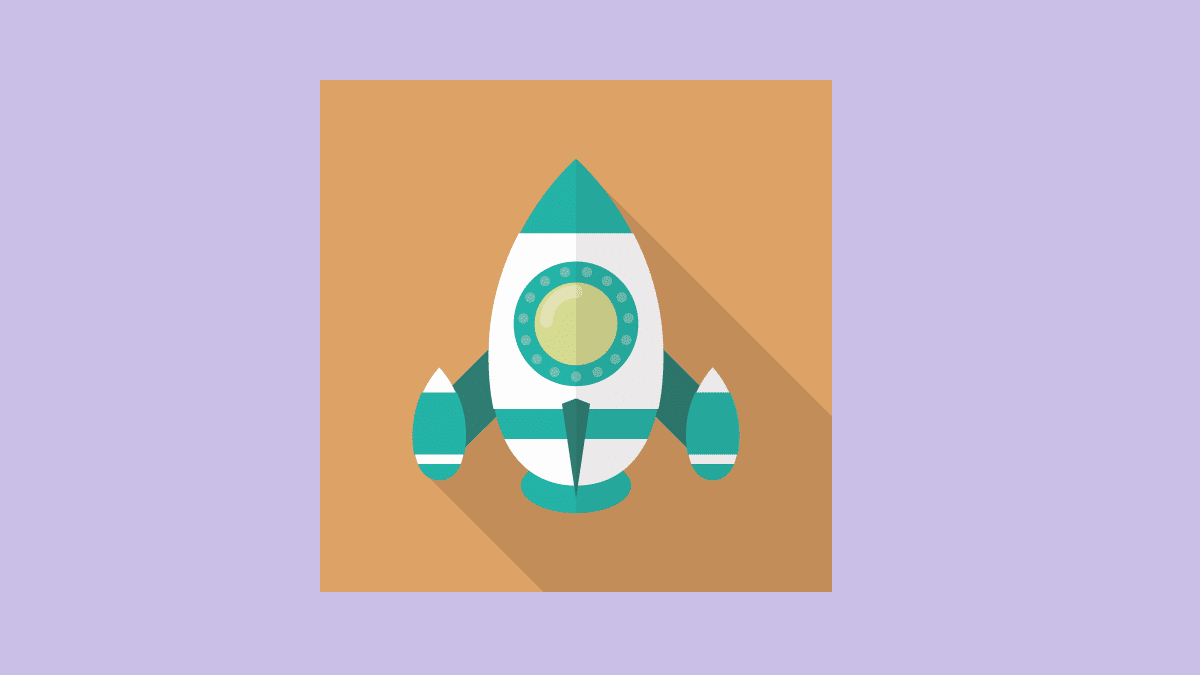TOEFL iBT Writing Section の Question 2 で高得点をとるコツは何だろう?どんな対策がいいのだろう?
以下は、このような疑問への回答です。
Writing Section 全体についての情報はこちら ↓ 。
Writing Section: Question 1 については、こちらを ↓ 。
最初に、Question 2 の問題形式や質問の傾向を検討します。その後、対策を考えます。TOEFLを作成しているETSが提供する例題やアドバイスを見てどのようにレスポンスを書けば良いのかを具体的に考えていきましょう。レスポンスのサンプルも見て頂きます。
Question 2 の問題形式
まず、 Question 2 の問題形式です。
Question 2 は「Writing for an Academic Discussion」とも呼ばれ、その内容は大学の授業に似ています。つまり、アカデミックな内容です。具体的にはオンライン・ディスカッションという形をとっています。教授の質問に対して、2人のクラスメートがそれぞれの考えを投稿しています。この状況で、自分の意見及び意見を裏付ける理由や具体例を書き、ディスカッションに貢献することが求められているのです。
Question 2 の持ち時間は、10分です。その間に、教授の質問や、クラスメートの投稿を読んで、自分の意見を書くことになります。レスポンスの長さ(単語数)は、100 words 以上が望ましいとされます。
Question 2 は、例えば次のような質問が出ます(出典はETSの練習問題サイトに掲載されているWriting for an Academic Discussion practice questionsの問題「Question 4」)。
Your professor is teaching a class on education. Write a post responding to the professor’s question.
In your response, you should do the following:
- Express and support your opinion.
- Make a contribution to the discussion in your own words.
An effective response will contain at least 100 words.
Doctor Achebe:
This week, we’ll look at how well students transition to university. Many recent high school graduates have taken a gap year — a yearlong break after graduation — before studying at a university. During a gap year, students may get jobs, travel, or simply relax and think about their future. Some students say their gap year was beneficial, while others regret having taken one. In your opinion, does taking a gap year create more advantages or disadvantages for students? Why?Andrew: The gap year would be a good opportunity for students to reflect on their education goals and confirm their plans for university. At least it would give someone time to investigate different fields and get a better sense of wheat it means to be in business, to work in an office, or to work with their hands, etc.
Claire: Because university can be expensive, students should not take a gap year. Tuition, the cost of books, and living expenses rise every year. The money a student might save during a gap year might not be enough to cover the rise in prices when they enter university a year later.
御覧のように、まず、授業の科目(分野)は何なのかという情報が与えられます。この例題の科目は教育ですね。そして、どのようなレスポンスを書くべきかということが示されています。具体的には、自分の意見及び意見を裏付ける理由を自分の言葉で書いて、ディスカッションに貢献することが求められているということです。
続いて、レスポンスの望ましい長さが示されています。単語数が、100語以上が望ましいと書かれています。
その下に、教授(この例題では Dr. Achebe)の投稿した質問(Question)が表示されています。質問の内容は、おおざっぱに和訳すると次の通りです。
高校を卒業した学生の中には、大学に進む前にギャップ・イヤー(卒業後1年間の休学期間)を取る者が多くいる。ギャップ・イヤーの間、学生は仕事(バイト)をしたり、旅行したり、あるいは単にリラックスして自分の将来について考えたりする。ギャップ・イヤーは有益だったと言う学生もいれば、ギャップイヤーを取ったことを後悔する学生もいる。ギャップ・イヤーを取ることは、学生にとってメリットとデメリットのどちらが大きいと思うか?そう思う理由は何か?
この教授の質問に対して、2人のクラスメート(AndrewとClaire)が自分の意見を投稿しています。
TOEFLの受験者は、クラスメートの意見も参考にしながらディスカッションに貢献するような意見を書くのです。
実際の TOEFLE iBT では、Writing の Question 2 が表示される画面の上端にタイマーがあり、Question 2 が始まるや否や、タイマーが「10:00」から動き出します。また、この画面の中にレスポンスを書く空白スペースがあり、その空白スペースの上端には、自分が書いた単語数が表示されます。(ETSの練習問題サイトに掲載されている例題を見て慣れておきましょう。)
では、質問の傾向と対策を考えていきましょう。
質問の傾向:【タイプ1】【タイプ2】
具体的には、どのような質問が出題されるのでしょうか。先ほど、すでに一例を見ましたが、ETS の練習問題サイトには、タイマー付きの練習用の例題が28題含まれています(この練習問題サイトではレスポンスをタイプすると、AIが点をつけてくれます)。また、タイマー付きではないですが答え方のヒント等も付いている「TOEFL iBT Writing Practice Sets」にも2題含まれています。これら30問をざっと見ると、大体の質問の傾向が見えてきます。
まずこの30問に含まれる分野・科目は科の通りです。
Education、environmental science、business administration、economics、sociology、public policy、career readiness、human resources management、child development、political science、film studies、
また、質問のタイプは、私が調べたところでは、おおむね次の2つのタイプに分かれます。
- 【タイプ1】 一つは、二択問題です。つまり、2つの選択肢からどちらを選ぶべきか、というような問題です。例えば、先ほど見た例題にあったように、「Does taking a gap year create more advantages or disadvantages for students?」のような文言が使われます。
- 【タイプ2】 二つ目のタイプは、「What scientific discovery or technological invention from the last two hundred years would you choose as being important?」のように、無数の選択肢が可能なテーマで、何か一つを選びそれについてなぜそれが重要だと思うのかを書きなさい、というような問題です。
対策
採点基準を参考にする
・レスポンスはETSの採点基準に基づいて、高得点が取れるように書くのが賢明です。採点基準や採点システムについては、こちらで説明しています。
ETSが提供するヒントを参考にする
上で触れたETSのTOEFL iBT Writing Practice Setsの中には、【タイプ1】と【タイプ2】の例題が含まれており、レスポンスの書き方に関するヒントも提供されています。まず、【タイプ1】の例題を見ていきます。
【タイプ1】
この例題及びヒントは、ETSのウェブサイトにある「TOEFL iBT® Practice Sets」のWriting Practice Set 2: (Academic Discussion) — Instructions, Question, and Discussionから転載しています。原文の大雑把な和訳を付けます。
まず例題です。
例題
Your professor is teaching a class on political science. Write a post responding to the professor’s question.
In your response you should:
• express and support your opinion
• make a contribution to the discussion
An effective response will contain at least 100 words. You will have 10 minutes to write it.
Dr. Gupta: As I mentioned in class, governments make public policies to describe their responses to various problems that affect a community. Part of this process involves setting and defending priorities about which issues deserve the most attention and resources. For example, governments need to decide whether they should spend more money on education or on environmental protections. If you were a policy maker, which issue would you argue is more important—education or environmental protections? Why?
Kelly: We all live on planet Earth, and it is the only planet we have. Therefore, we must take care of it. Clearly, protecting the environment should be the government’s priority over education. I think the REAL question is, which approach to protecting the environment—restricting pollution, regulating population, promoting clean energy, or something else—should be the government’s priority.
Andrew: I disagree with Kelly that that the environment is more important than education. Education is actually the best way to protect the environment. Educated people can see how their decisions affect the world around them. Also, with better science and technology education, we can develop solutions to environmental problems. Therefore, I think the government should spend more money on education.
レスポンスには:
– 自分の意見及び意見を裏付けるもの(理由や具体例)を含めなさい。
– ディスカッションに貢献する内容を含めなさい。
効果的なレスポンスを書くためには、100語以上の長さが必要です。持ち時間は10分です。
グプタ教授: 授業で話したように、政府は社会に影響を与えるさまざまな問題への対応を示すために公共政策を決定する。その際、どの問題が最も注目に値し、資源を投資して対応すべき最重要課題であるかという優先順位を設定し、それを優先する正当性を説明する必要がある。例えば、政府は教育にもっとお金をかけるべきか、それとも環境保護にもっと資金を費やすべきかを決める必要がある。あなたが政策立案者なら、教育と環境保護のどちらが重要だと主張するか?その理由はなぜか?
ケリー: 私たちは皆、地球という星に住んでいる。従って、私たちは地球を大切にしなければならない。環境保護が教育よりも優先されるべきなのは明らかだ。問題は、公害の規制、人口規制、クリーンエネルギーの推進など、どういったアプローチで環境を守ることを優先すべきかということだ。
アンドリュー: 教育よりも環境の方が重要だというケリーの意見には賛成できない。教育こそが環境を守る最善の方法だ。教育を受けた人は、自分の決定が周囲の世界にどのような影響を与えるかを知ることができる。また、科学技術教育を充実させれば、環境問題の解決策を開発することができる。従って、政府は教育にもっとお金を使うべきだ。
次に高得点を取るためのヒントです。
ETS提供のヒント
Writing Practice Set 2: (Academic Discussion) — Response Tips
To earn a top score, you should state and support your opinion about whether education or environmental protections should be the priority for governments to spend money on. Your response is a contribution to the other two students’ posts in an online discussion for the class. Be sure to add your own perspective to the discussion, not merely repeat ideas that have already been stated. Typically, an effective response will contain a minimum of 100 words.
You might agree with Kelly that environmental protections should be the priority. You will need to add your own support for this viewpoint. For example, you could argue that environmental protections are a more important investment to sustain our economies. You could point out that governments currently spend a great deal of money compensating for climate change catastrophes such as increased flooding, wind damage, or ruined crops. Investing more in environmental protections now could actually save governments money later on—which could then be used for more education funding. This would differ from the support Kelly gave for her opinion.
If you agree with Andrew that education should be the bigger priority, you could add to his argument by pointing out the amount of research that universities conduct—not only on solving environmental problems, which Andrew alluded to, but also on treating diseases, creating useful technology, and developing sustainable agriculture. Therefore, education funding has a bigger overall impact on improving human lives than investment in environmental protections only. This would be a meaningful addition to the support Andrew provided for his opinion.
You may find you agree with a point Kelly made about the environment even though you think education is more important. Or you might even find that your opinion about government priorities depends on certain factors—that education should be a priority in some circumstances, environmental protections in others. This is perfectly acceptable as long as you explain and support your reasoning. There is no “correct” answer to the question. The important part of this task is to make sure that you state your opinion and provide reasonable, relevant support for it in a way that makes a meaningful contribution to the online discussion. Try to develop your opinion as well as you can within the time limit. A well-developed response will contain clearly appropriate reasons, examples, and details—ones that do a good job supporting or illustrating your own viewpoint.
The quality and accuracy of the sentence structure and vocabulary you use to express your ideas is also very important and part of what is considered when your response is scored. The task context—a post to an online discussion group—is not quite as informal as you might think. While the task asks you to contribute to a discussion with fellow students, imagine that the professor would also be reading your post. It is true that your tone might be more casual than what you would use in an academic paper, but you should still follow standard grammar rules. Also, if disagreeing with another student post, be sure to express your disagreement in a respectful way as you would in a real online discussion.
This task is scored using the Academic Discussion Rubric.
【タイプ2】
タイプ2の例題及びヒントも、ETSのウェブサイトから転載します。「TOEFL iBT® Practice Sets」のWriting Practice Set 4: (Academic Discussion) — Instructions, Question, and Discussionです。原文の大雑把な和訳を原文の下に付けます。
まず例題です。
例題
Writing Practice Set 4: (Academic Discussion) — Instructions, Question and Discussion
Your professor is teaching a class on economics. Write a post responding to the professor’s question.
In your response you should:
• express and support your opinion
• make a contribution to the discussion
An effective response will contain at least 100 words. You will have 10 minutes to write it.
Dr. Achebe: When people are asked about the most important discoveries or inventions made in the last two hundred years, they usually mention something very obvious, like the computer or the cell phone. But there are thousands of other discoveries or inventions that have had a huge impact on how we live today. What scientific discovery or technological invention from the last two hundred years—other than computers and cell phones—would you choose as being important? Why?
Paul: I mean, we’re so used to science and technology that we are not even aware of all the things we use in our daily lives. I would probably choose space satellites. This technology happened in the last hundred years, and it has become important for so many things. Just think about navigation, or telecommunications, or even the military.
Claire: I am thinking about medical progress. Like, for example, when scientists discovered things about healthy nutrition. I am thinking of identifying all the vitamins we need to stay healthy. I am not sure exactly when the vitamin discoveries happened, but I know they are very important. Our health is much better than it was 200 years ago.
レスポンスには:
– 自分の意見及び意見を裏付けるもの(理由や具体例)を含めなさい。
– ディスカッションに貢献する内容を含めなさい。
効果的なレスポンスを書くためには、100語以上の長さが必要です。持ち時間は10分です。
アチェベ教授: 過去200年間になされた最も重要な発見や発明について尋ねられると、たいていはコンピューターや携帯電話のようなごく当たり前のものを挙げる。しかし、今日の私たちの生活に大きな影響を与えた発見や発明は、他にも何千とある。過去200年間の科学的発見や技術発明のうち、コンピューターや携帯電話以外で重要だと思うものを選ぶとすれば、何を選ぶか?それを選ぶ理由はなぜか?
ポール: 私たちは科学技術に慣れすぎていて、日常生活で使っているものすべてに気づいていない。私なら人工衛星を選ぶ。人工衛星の技術はここ100年の間に生まれたもので、多くの分野で重要な役割を果たすようになった。例えば、ナビや電気通信、あるいは軍事について考えればその重要性が分かる。
クレア: 私は医学の進歩の重要性をあげる。例えば、健康に欠かせない栄養についての発見は大変重要だ。健康を維持するために必要なすべてのビタミンを特定できたは特筆すべきことだ。ビタミンの発見がいつ起こったのか正確にはわからないが、とても重要なことだというのはわかる。私たちの健康状態は200年前に比較すると大幅に改善されている。
次に、ETSのウェブサイトに掲載のサンプル・レスポンスです。これは満点、つまり「5」の評価を得たレスポンスです。原文の後に和訳を付けます。
Response A, Score of 5
In the past 200 years, tons of scientific discoveries or technological inventions have been shown to the world. If I had to choose one in particular it will probably be vaccine or antibiotics. With Pasteur’s work and discoveries, the world changed in a way people couldn’t imagine. So many people were dying really young because at that time life’s conditions were not as good as the one we have now. With vaccine, we could now irradicate diseases that were killing millions of people, we learn so much about the immune system and ways our body was reacting to pathogens and the answers he could produce to defend us against it. Medicine evolved so much and keeps evolving every day because scientists are curious to understand how our body is working and how he is able to communicate with our environment. People aged 40 are now not that old and still have a really long life to live and enjoy when 2 centuries ago it was synonymous of 80% chance of dying.
このレスポンスが「5」の評価を得た理由も、ETSのウェブサイトに掲載されていますので、ここに転載し原文の後に和訳を付けます。
Score explanation
This is a fully successful response. The writer chooses vaccines/antibiotics as the most important invention of the past 200 years. The author then provides a description, for contrast, of what life was like before Pasteur’s work (people dying young) and after the vaccine was created (millions of lives saved, more understanding of the immune system). The writer continues on to point out that medicine continues to evolve because of Pasteur’s work and how human lifespans have been extended. Overall, the response provides well-elaborated explanations and details to support the main opinion and provides a relevant contribution to the discussion.
While there are almost no errors in grammar and word choice, there are a few minor ones that have little impact on meaning (such as “life’s conditions were not as good as the one we have” rather than “were not as good as they are now,” and “how our body is working and how he is able to communicate” rather than “how it is able to communicate”). However, these errors are fairly minor and such errors might be expected when writing under timed conditions. The writer is able to use some complex sentences and relatively precise vocabulary, which is expected in a 5-level response.
以上、ETSの資料を見ていただきました。
サンプル・レスポンス
それでは、具体的に書き方を説明していきます。
上で最初に見た練習問題サイトのQuestion 4を使って、サンプル・レスポンスをお見せしながら、進めます。この例題は、 【タイプ1】の問題、つまり、いわゆる二択問題です。
ちなみに、【タイプ2】の問題のサンプル・レスポンスをご覧になりたい方は、こちらをどうぞ。
ここでお示しするサンプル・レスポンスでは、ギャップ・イヤーを取ることは、学生にとってメリットとデメリットの両方ともあり、有益なのかどうかは、学生個人の目的(求めているもの)や状況次第だ、という意見を書いていきます。
アウトラインをメモする(約2分以内)
いきなりレスポンスを書いてもかまいませんが、まず、どのような議論を展開するかをざっと考えることをお勧めします(2分以内)。自分の意見を決めて、書きとめて、この意見を裏付けるポイント(理由や例)を2つか3つ考えます。そして、それぞれのポイントを説明する詳細情報等を考えて、思いついたことを素早く書きとめておくのです。
私は下のようにアウトラインを書いていますが、自分にとって意味を成すものであればどんなアウトラインでも構いません。英語・日本語混在でも構いません。また、私は時間制限がない状態でこれを書いていますので、かなりたくさんの情報を書き留めていますが、これほど詳しいアウトラインを作成する必要はありません。実際に TOEFL iBT を受けるときは、とにかく思いつくことを書き留めて、レスポンスを書くための情報収集と情報整理をするんだ、という気持ちでアウトラインを書いてください。また、アウトラインはきれいに整然と書く必要もありません。例えば、最初に思いついたときは1つ目のポイントの詳細情報にしようと思って書き留めたけれど、あとで、これは2つ目のポイントのサポートとして使える情報だと思ったら、線や矢印で、それを示しておけばいいですね。
Outline
意見:both advantages and disadvantages; depends on individual goals and circumstances.
1つ目のポイント:Advantages (experiences)
Skills thru work
Broaden perspectives thru travel
Develop direction
Break from pressures
2つ目のポイント: Drawbacks
Lose momentum
Feel out of sync w/ peers
Challenges when readjusting
Financial considerations
結論: 上のまとめ
レスポンスを書く(サンプル・レスポンス)
それではアウトラインのメモを基にしてレスポンスを書きます。
教授の質問に対して意見を述べているクラスメートの投稿に言及をすることが、ディスカッションに対する貢献になると思ったら、何らかの言及をすることも賢明です。しかし、必ず必要であるというわけではありません。
また、クラスメートの投稿に言及するといっても、クラスメートの意見を繰り返すにとどまり、自分独自の考えを述べないというようなレスポンスは、ディスカッションに貢献することにならないため、得点は低くなります。注意が必要です。
意見: 自分の意見をはっきりと書きます。Taking a gap year can offer both advantages and disadvantages for students, and the impact largely depends on individual goals and circumstances.
1つ目のポイント: メリットについて書きます。ここで主張する内容の一部はAndrewの意見と重なりますので、それに言及します。
On the positive side, a gap year can provide valuable life experiences, allowing students to gain practical skills through employment, broaden their perspectives through travel, and, as Andrew rightly notes, develop a clearer sense of direction for their future studies. Moreover, it can offer a break from the academic pressures, promoting mental well-being and preventing burnout.
2つ目のポイント: デメリットについて書きます。ここでも、一部はすでに投稿しているクラスメートの意見に重なりますので、Claireに言及します。
However, there are potential drawbacks, such as the risk of losing academic momentum, feeling out of sync with peers, or facing challenges when readjusting to a structured academic environment. As Claire suggests, financial considerations may also come into play.
結論: 結論は不要ですが、入れてもかまいません。ただし、既に述べてきた内容以外の新たなポイントは書いてはいけません。
結論を書くのなら、上で述べてきたことに言及して、最初に述べた意見を、少し文言を変えて書きます。たとえば、このように書けばいいですね。
Ultimately, whether a gap year is beneficial or not depends on the individual’s objectives, readiness for university, and the activities undertaken during the break.
ETS提供の例題に取り組む
対策として非常に有効なのは、上で触れた28題の練習問題が用意されているETSのWriting for an Academic Discussion Practice QuestionsやETSのTOEFL iBT Writing Practice Setsにある2つの例題を使って練習するのが非常に効果的です。特に、前者の28題は本番の問題の模擬試験のようなものです。タイマーが付いており10分で自動的に終わらざるを得ないため、本気で問題に取り組む気持ちになれます。また、すでに述べたように点数もつけてくれます。AIのみによる採点で精度は本番の採点よりも劣りますが、かなり有益です。練習をする気になります。なるべくたくさんの練習問題に取り組みましょう。また、同じ問題に何度も挑戦するということも有益な練習方法です。
便利な接続表現
最後にレスポンスを書くときに便利な表現をいくつかリストアップします。
In addition. . . .(その上、さらに、加えて)
Moreover. . . .(さらに、その上に、また)
Furthermore. . . .(そのうえ、さらに)
Also. . . .(また、それに)
In other words. . . .(言い換えると)
So. . . .(したがって)
In fact. . . .(実は、実際のところ)
However. . . .(しかし)
Yet. . . .(しかし)
(On the one hand. . . .) On the other hand. . . .(他方で)
Nevertheless. . . .(しかしながら)
Nonetheless. . . .(しかしながら)
Having said that. . . .(とは言え)
That said. . . .(とは言え)
One (of the advantages) is (that). . . .(利点の一つは)
One (of the benefits) is (that) . . . .(利点の一つは)
One argument in favor is that. . . .(それを支持する1つの議論は)
Another advantage is (that) . . . .(もう一つの利点は)
A further benefit is (that). . . .(もう一つの利点は)
One other positive aspect is (that). . . .(もう一つの利点は)
One (of the disadvantages) is (that) . . . .(一つの欠点は)
One (of the drawbacks) is (that) . . . .(一つの欠点は)
Another disadvantage is (that) . . . .(もう一つの欠点は)
A further negative aspect is (that) . . . .(もう一つの欠点は)
One other disadvantage is (that) . . . .(もう一つの欠点は)
This is because. . . .(その理由は)
One reason (why . . .) is (that) . . . .(一つの理由は)
One of the (main) reasons (why . . .) is (that) . . . .(一つの理由は)
Another reason is. . . .(もう一つの理由は)
A further reason is (that) . . . .(もう一つの理由は)
Part of the reason (why . . .) is (that) . . . .(理由の1つは)
As a result of ~(~の結果として、~を受けて)
For this reason. . . .(この理由から、このような訳で)
Therefore. . . .(したがって)
That is why. . . .(したがって)
It is worth noting that ~(~は注目に値する)
We can say that ~(~と言ってよい)
It is important to note {recognize} {emphasize} that ~(~は重要である)
It goes without saying that ~(~は言うまでもない)
例を挙げるときに便利な表現:
For instance. . . .(たとえば)
For example. . . .(たとえば)
Take ~ for instance. . . .(例えば~を見て{検討して}みよう)
~ is a good example. . . .(~は良い例だ)
~ is a case in point. . . .(~は、それの良い例だ)
A common example (of this) is when. . . .(良く知られた具体例は)
* * * * * *
★ TOEFL 必須語彙のおすすめ教材をこちらで紹介しています。ご覧ください。